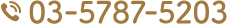嚥下障害とは

また、上手く飲み込めないことで「栄養不良」、「窒息」、「脱水症状」、「誤嚥性肺炎」の原因にもなることもあります。
嚥下障害の症状
- 唾液が飲み込めず口から出してしまう
- 食事中に咳が出たりムセることがある
- 食事に時間がかかり疲れてしまい、最後まで食べきれない
- 痰が多く喉がゴロゴロする
- 固形物は噛まないと飲み込めないため柔らかいものばかり食べてしまう
- 食事の後声がかすれたりガラガラ声になる
- 体重減少
嚥下障害の原因
嚥下障害の原因は「器質的原因」「機能的原因」「心理的原因」の3つに大きく分けられます。
器質的原因
嚥下に関わる身体器官の構造上の問題があり、うまく嚥下ができなくなる場合です。
例えば、口内炎や喉頭がんや食道がんなどの炎症や腫瘍、あるいは唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)などの先天的な奇形が原因となることもあります。
機能的原因
器官の構造そのものには問題がなく、飲みこむ動きに必要な筋肉や神経機能に問題があり、嚥下に障害が起こるケースです。
運動麻痺や認知機能障害を引き起こす「脳血管疾患(=脳卒中)」、あるいは「パーキンソン病」などの「神経筋変性疾患」が原因の場合があります。
向精神薬や鎮静剤などの薬剤の影響で必要な各器官の働きが抑制されることもあります。
また、加齢により咀嚼や嚥下に必要な筋力が衰えると飲み込むときに気道を閉じることができなくなり、食べ物が気管に入りやすくなります。
これにより食べ物が気管に入ってしまう「誤嚥性肺炎」が起こりやすくなり致命的となることがあります。
心理的原因
うつ病や心身症など、心因性の疾患が原因で嚥下障害を引き起こす場合もあります。
心因性の嚥下障害は、食事を摂る際に嚥下困難を感じることは少なく、唾液を飲み込む時に異物感が強くなるという特徴があります。
*当院の嚥下外来では、“嚥下障害の可能性のある方”すべてを対象に評価・検査を行っています。
嚥下障害でよく見られる症状
- 食べるのが遅くなった
- やせてきた
- 食べこぼす
- 口の中に食べ物が残る
- のどの奥に食べ物が残る
- 食事中にむせる
- 痰が多い
- のどがゴロゴロ鳴る
- 風邪以外で熱が出ることがある
- 食べ物がつかえる
- 飲み込みにくい
- 食べ物や胃液が逆流する
- 咳が出る
嚥下内視鏡検査
当院では、嚥下内視鏡によって嚥下障害の機能診断を行い、食事を楽しむための指導や訓練方法の指導を行うことができます。
嚥下機能の評価
嚥下機能の検査には
嚥下内視鏡検査(videoendoscopic examination of swallowing :VE)
内視鏡を鼻からのどに入れ、実際にものを飲み込む状態を内視鏡で観察する検査です。最初の評価では、飲み込むものとして、青く着色した水などが使われます。
嚥下造影検査(videofluoroscopic examination of swallowing :VF)
X線を照射しながら造影剤を飲み込む検査です。口の中から、のどを通り食道 まで、造影剤がどのように流れていくかを見ることができます。
嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査にもそれぞれメリット・デメリットがあります。 当院では外来で嚥下内視鏡検査を行っています。
嚥下内視鏡検査は、嚥下時の咽頭の状態を直接に目で観察できる唯一の検査で、
- 被爆がない
- 外来で簡単に検査ができる
- 何度でも繰り返して行うことができ、その結果を比較することができる
などのメリットがあります。
嚥下内視鏡検査では、実際に液体や固形物を飲み込んでいただきながら、その際ののど(咽頭や喉頭)の状態を内視鏡を使って観察します。
青色に着色された水やトロミをつけた着色水、時にゼリーなどの固形物を用いて嚥下状態を評価します。
検査は、診察用の椅子に座った状態で行い、径が3㎜以下の細い内視鏡を使いますので、胃・食道の検査などと違い麻酔は特に必要としませんが、場合によって鼻腔内局所の簡単な表面麻酔だけ行います。
検査時間については、特別なリハビリ的処置を行う場合を除き、おおむね30分以内を目安としております。
当院ではまず嚥下内視鏡検査を行い、その後、必要に応じて、嚥下造影検査を追加するということにしており、嚥下造影検査は提携医療機関にお願いして行っていただいております。
嚥下リハビリテーション
嚥下障害の改善にはリハビリテーションが効果的です。嚥下訓練は
- 食物を用いないで行う間接訓練(基礎訓練)
- 食物を用いる直接訓練(経口摂取訓練)
の二つに分けられます。
また、具体的な訓練法としては、代償的アプローチ法と治療的アプローチ法があります。
代償的アプローチ法
現状の嚥下機能を最大限に活用して誤嚥のリスクを最小限にすることを目指した工夫で、嚥下姿勢や食形態の調整・選択などとなります。
治療的アプローチ法
麻痺や障害を受けた部分に働きかけて、嚥下機能の代償や補強・改善を目指した訓練です。
- 嚥下反射惹起を促すための訓練
- 嚥下関連器官の機能訓練
- 咽頭期嚥下の改善・強化訓練
- 嚥下パターン訓練
当院では、原因となっている病態と嚥下内視鏡検査などの結果と総合的に判断して、その方に合った訓練の組み合わせを考えて行っております。
嚥下障害の外科的治療
嚥下障害の治療は、まず、前述の嚥下訓練が行われます。
しかし、どうしても嚥下訓練が奏功しない場合、外科的治療すなわち手術が検討されます。
この嚥下障害に対する手術には、
「誤嚥防止手術」:高度の嚥下障害で肺炎を反復するような場合に行われる手術
これらの手術には色々な手術法がありますが、当院では、これらの手術自体は行っておりません。
検査や嚥下訓練の経過により、手術が必要と判断した場合には手術可能な病院に御紹介して手術を行っていただくことにしております。
嚥下障害は、栄養という側面も非常に重要です。
当院では嚥下障害によって不足する栄養に関して、様々な角度からアドバイスを行います。
また、体組成計を用いて身体の筋肉の量を測定し栄養状態の評価の参考とします。